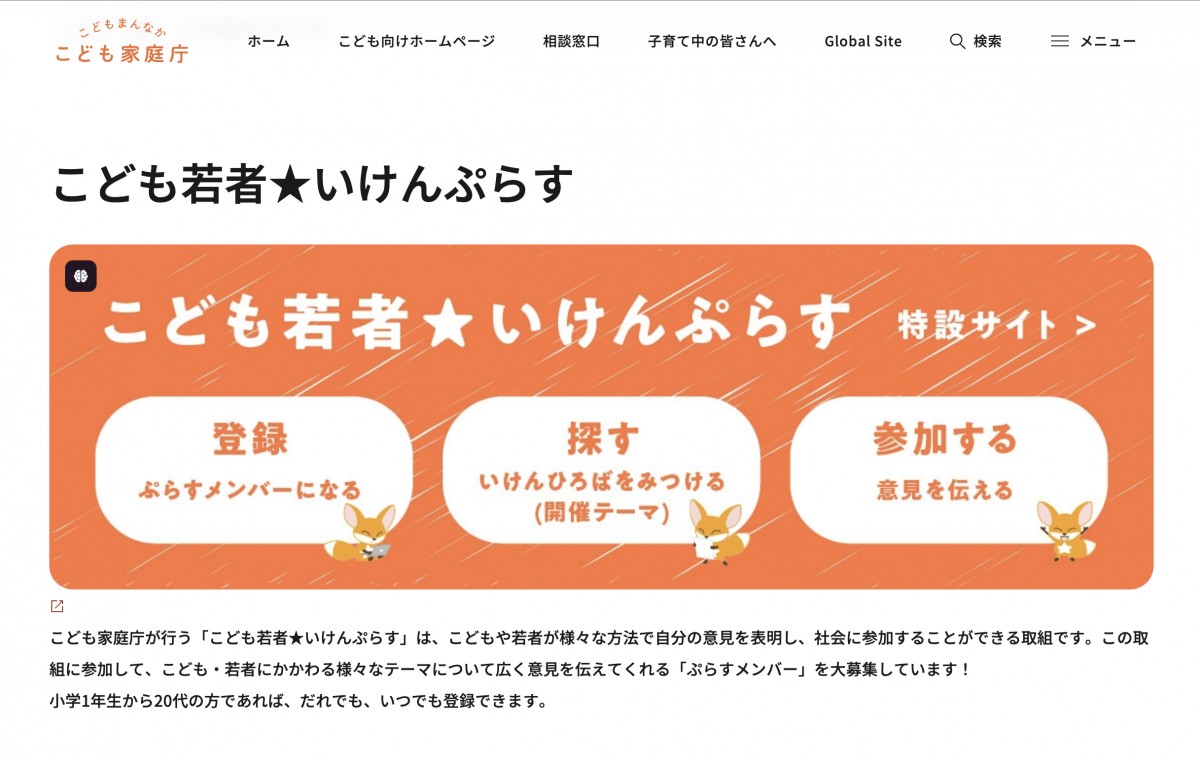デイリーWiLL 1/3配信回の補足
私の体調や家の都合等々でしばらくお休みしていましたが、体の調子が戻り、家のことも落ち着いたタイミングで、「選択的夫婦別姓について近藤さんのお話が聞きたい」と出演依頼を受けて、この度収録をしました。
デイリーWiLLお休みの期間に少し他の番組に出たりはしていましたが、やっぱり信頼している山根さんとの収録は、なんだか実家に戻ってきたような安心感があって、素のリアクションが出てしまいました(笑)
メガネの山根さんに驚く近藤倫子www
今回の動画内では、まず選択的夫婦別姓の世論調査の不自然さについて語っています。
推進派が出している世論調査というものは、NHKの放送内で使用された「賛成or反対」の二択のみでの調査結果です。

番組内でもお伝えしたように、「賛成か、反対か」との質問は、答えが二つしかないので自分事として捉えていない内容に対しては「賛成」と答えてしまう傾向があります。このNHKの放送内で使用された調査結果がまさにそれです。
しかし制度には賛成でも「自分は夫婦同姓がいい」と答えている若い女性がいます。読売新聞オンラインで確認することができます。
制度導入には賛成と答えた女性の38%が「自分は夫婦同姓がいい」と答えていることがこのグラフから分かります。
この円グラフを世代別に抽出したものを見ると、20代女性の半数が「自分は夫婦同姓がいい」と答えています。30代女性でも「自分は夫婦同姓がいい」と答えている人が42%、夫婦別姓を選択すると言っている人よりも多いことが判ります。
20代・30代の働く女性はこれから結婚する可能性があり、「選択夫婦別姓制度」の当事者ですから、この「自分は夫婦同姓がいい」との調査結果は重要なことを示唆しているといえます。
番組内でもお伝えしましたが、「自分は夫婦同姓がいい」と当事者が言うのですから、制度として導入する必要は全くないのです。
番組内で使用したこちらの調査結果は、私がいつもXで添付している資料ですので皆さんもしっかりと頭に入っていると思います。日本政策研究センターで出しているものです。
より見やすくするために一つずつ画像を貼っていきます。
まずは読売新聞の世論調査です。

①「(今の制度を維持しつつ)通称として結婚前の名字を使える機会を拡大する」47%
②「夫婦は同じ名字とする今の制度を維持する」20%
③「選択的夫婦別姓制度を導入する」28%
①と②は「夫婦同姓制度を維持する」となっていますから、、現行のままでいいと答えている人は67%です、対して選択的夫婦別姓を望む人は28%です。私がいつも「国民の7割が反対している」というのは、この世論調査の結果を踏まえてのことです。
次は内閣府とJNNの世論調査の結果を貼ります。こちらも日本政策研究センターのものです。

先ほどの読売世論調査と同じく設問は三択です。
①「(今の制度を維持しつつ)通称として結婚前の名字を使える機会を拡大する」42.2%と47%
②「夫婦は同じ名字とする今の制度を維持する」27%と21%
③「選択的夫婦別姓制度を導入する」28.9%と26%
こちらの調査結果でも①と②の合計は69.2%と68%ですから、現行のままの夫婦同姓を望む人は7割といえます。
このようにして選択肢が3つある世論調査を見ると、推進派が言っている「賛成が多数」というのは間違っていると言えるのです。
推進派の方からのコメントで「近藤はいつも同じ調査結果しか使っていない」と言われますので、新しい調査結果を公開します。こちらは私が出演した『赤坂ニュース』(参政党チャンネル)からの転載です。
産経新聞・FNNの合同世論調査の結果です。向かって左側は「賛成or反対」の二択の質問。向かって右側は三択の設問です。やはり夫婦同姓維持と夫婦同姓を維持したうえでの旧姓通称使用が多く合計で58.5%、半数以上が夫婦別姓に反対であると言えることがこちらの調査結果からも判明しました。
やはり、推進派の言う「夫婦別姓賛成多数」は嘘でしたね。
中高生の意識調査アンケートでも、夫婦別姓に反対の意見は9割です。
「あなたは、将来、結婚したとしたら、名字をどのようにしたいと思いますか?」
向かって左側の橙色は「相手の名字を、自分の名字に変えてほしい」(以下①と表記)18%
その隣の山吹色は「自分の名字を、相手の名字に変えたい」(以下②と表記)15%
藤色は「自分の名字でも、相手の名字でも、どちらでも構わない」(以下③と表記)59%
若草色は「自分も相手も、名字を変えずにそのままでたい」(以下④と表記)7%
一番右側の灰色は「無回答」2%となっています。
①は相手が自分の名字に改姓して同じ姓を名乗りたい=夫婦同姓、②は自分が相手の名字にする=夫婦同姓、③はどちらが変えてもいいけど同じ姓にする=夫婦同姓、と解釈するのが自然なのではないかと私は考えます。ですので①②③を足すと合計は92%、中高生の9割は夫婦同姓がいいと言っていることが判ります。
対して夫婦別姓を望む中高生はわずか7%です。もちろん児童福祉の理念の一つである「子どもの意見の尊重」を踏まえるとわずか7%でも、その意見は汲み取る必要があるとは思いますが、だからといって92%の中高生の意見を無視する行いは民主主義ではありません。
「中高生の9割が夫婦別姓に反対している」と私が言っているのは、決して間違いではないのです。
デイリーWiLLの1/3配信回の補足ではないのですが、収録が昨年の12/30でしたので、扱えなかったこちらの調査結果について書きます。↓
本年元日、産経新聞で報道された小中生の半数が夫婦別姓に反対だとの調査結果。
「新しい法律で家族が違う名字になったとしたら、賛成ですか、反対ですか」
回答は二択ですので、私が「賛成or反対」の二択での質問は良くないと言った観点からは外れてしまいますが、夫婦別姓に関する世論調査は主に成人を対象にしたものが多く、先ほどの中高生より下の世代である小学生に対して調査を行ったのは産経新聞が初めてです。
選択的夫婦別姓制度の当事者は子供達です。これから結婚をする大人も当事者ですが、小学生にとっては強制的に父または母と違う姓を強いられるのですから、子供達は当事者であるといえます。
質問に書いてある「新しい法律」とは選択的夫婦別姓制度のことですから、これに対して49.4%の小中生が反対と答えています。両親、兄弟姉妹で名字が変わる事に対して子供達は「反対」だと言っています。
「親が決めたのなら賛成」とは、消極的な賛成だと私は解釈しています。このセリフは両親が離婚する場合によく耳にするものです。「自分はお父さんお母さんと一緒にいたいけど、親が決めたのなら仕方ない」、「親が離婚を決めたのなら賛成する」。私はこのような言葉を聞くといつも寂しい気持ちになります。子供の意見ではなく「親が決めたのなら…」積極的に賛成するならこのような言い方にはならないと思います。寂しそうな子供の顔が浮かびます。
この記事が公表された途端、推進派の方々はまるでヒステリーのように反応しました。
「子供はどうせ分かってない」だの「小中生の意見なんて、産経は◯◯だな」といったXポストが多数ありました。中には朝日新聞の記者を名乗るアカウントもありました。朝日新聞はこれまで多数の「子供の人権」「児童権利条約」に関する記事を掲載してきました、にも関わらず、自分たちにとって都合の悪い子供の意見が出ると、それを否定する。「子供の権利」を謳っておいてなんとも酷い有様です。朝日はやはり二枚舌、ダブルスタンダードな信用できない新聞社であることが再確認できました。
「子供はどうせ分かってない」という推進派にはぜひこの結果を見てほしいと思います↓
「よく知っていた」16%、「少し知っていた」37.1%、合計すると53.1%の子供達が「選択的夫婦別姓」について理解をしていました。調査対象となる小中生は小学生(4年生以上)が150人、中学生(全学年)が1800人ですから、中学生ともなれば高校受験の勉強のために新聞やニュースを日頃から見ている生徒もいるでしょう。世の中の動きをちゃんと見ている中学生がいるのは全く不自然ではありません。「子供はどうせ分かっていない」という人の方がなんにも分かっていないと私は思います。
それに対して「全く知らなかった」「ほとんど知らなかった」と答えた小中生は46.9%。これもおかしなことではありません。塾や習い事で忙しい今の子供達はゆっくり新聞やニュースを見る時間もありません。しかしこの調査を行うにあたって教師や民間の調査会社の方が説明をしたと記事には書いてありますので、これからの流れに興味を持った子供達が増えたと思います。
次は「自分が結婚する時に別の名字で結婚できるとしたら、どうしますか」との質問です。
私はこの質問には注意力が必要だなと感じました。この一文は「結婚するときに名字を選択できる(選択的夫婦別姓)としたら、あなたはどうしますか?」との意味ですので…。
「別々の名字にしたくない」59.9%
「別々の名字にしたい」13.6%
次世代を担っていく子供達の意見は重要です、その子供達は半数以上が「別々の名字にしたくない」と言っています。
私ははっきり言って、この「別々の名字にしたくない」59.9%が正しい意見だと感じます。
今後大人となり結婚をするであろう子供達は、夫婦別姓議論の当事者です。これ以上の調査結果はないはずです。だからこそ、推進派はヒステリー状態になっているのでしょう。そして子供の権利条約で規定している「子供の意見の尊重」をしないのです、自分たちの思惑が明らかにされてしまうから。
子どもの権利条約では「子供の最善の利益」も謳っています。子供にとって最も良いことを社会全体で考え、それを実行していくことが国と大人の責任であると書いてあります。
こども家庭庁も「子供の最善の利益」と「子供の意見の尊重」を謳っており、これらに基づいた政策として「こども若者★いけんぷらす」を行っています。
私がこども家庭庁長官の三原じゅん子氏に訴えているのは、こう言った理由からです。
今こそ、「子供の最善の利益」と「子供の意見の尊重」をする時なのではないでしょうか。
デイリーWiLLでの資料補足に戻ります。
番組内でマズローの欲求階層説に触れましたが、時間の都合で詳細を割愛しましたので、こちらにて説明をします。

(こちらの画像は私が講義の時に作成したものですので、無断転用は避けて下さい)
マズローの欲求階層説は、人間には欲求階層があり、一つ下の欲求が満たされると次の欲求を満たそうとし、絶えず自己実現に向かって成長するという考え方です。下段から積み上げていくようにして本能としての心の欲求が満たされ、心が安定します。
欠乏欲求と言われる本能の欲求が満たされる事によって成長欲求が生まれ、心の発達は進んでいきます。子供の心の発達にとって欠乏欲求が満たされる事は非常に大切なことで、一つずつ満たされていかないと、成長欲求に発展せず、自己実現欲求が生まれません。
私が番組内でお伝えした「社会的欲求」は集団に所属したいという欲求であり、幼児(子供)にとっての集団とは家族のことです。家族の一員であるとの実感が社会的欲求を満たし、承認欲求へと発展します。承認欲求は他者から存在を認められたいという欲求ですので、子供にとっては親、先生、友達が「他者」の相当します。両親のどちらかと違う姓を強いられた子供の心は、社会的欲求を満たしません、姓の違いを通して家族との一体感を実感できないと言えるからです。家族との一体感を得られない子供は、本能の欲求が満たされませんので、心が不安定となるでしょう。心が不安定なまま承認欲求が生まれれば、昨今問題となっている「承認欲求モンスター(承認欲求が強すぎて暴走した人物を指す俗称)」となってしまいます。子供の心の発達にも、親と同じ姓であること、家族との一体感は必要不可欠なのです。
推進派は「アイデンティティの喪失」を選択的夫婦別姓実現の理由に挙げていますので、エリクソンのライフサイクル理論を用いるのが適切だとも思うのですが、「家族という集団への帰属」という観点で見るとマズローも「社会的欲求」を挙げていますので、番組ではマズローを用いました。
山根さんとの収録は実家に戻ったような安心感がありますので、山のように用意した資料を使って冷静に一つずつお話しすることが出来ませんでしたので😅、今回はこちらで補足をしました。
1/6にもデイリーWiLL近藤出演回が配信されていますので、補足が必要な箇所があればまたメルマガ内で書こうかなって思います。
「りんこスイーツ部」入部はこちら😊↓
年末年始はとっても慌ただしくて、ゆっくりスイーツを堪能する時間がありませんでした。その代わりと言ってはなんですが、今回は関東では手に入らなくなった幻のこちらです・:*+.\(( °ω° ))/.:+

ジャーン!!!
大阪に帰省していた3人娘が箱買いをしてくれました☆
そういえば、番組内で言った「娘たちにヘアーアイロンを持っていかれてしまって…」とは、娘たちがヘアーアイロンを大阪に持って行ってしまったので、収録日は頭がボサボサだったのです💦
…というわけで、また次回の部活でお会いしましょう😊
🔳近藤倫子(こんどうりんこ)1975年生、日本女子大学卒。児童家庭支援士、著述家。月刊WiLL、Gakken、展転社等での執筆と連載。夕刊フジへの寄稿。デイリーWiLLをはじめとするネット番組多数出演。子供の心の発達に関する講演、子育てや日本を伝える講演会も多数登壇。
すでに登録済みの方は こちら